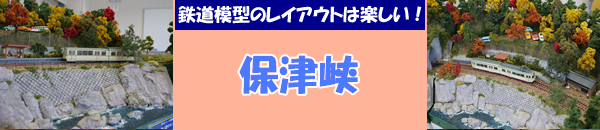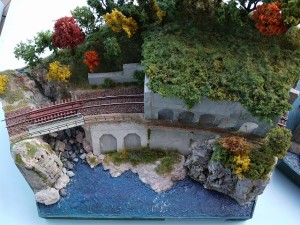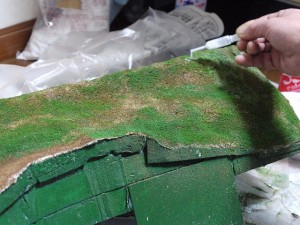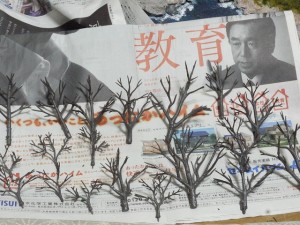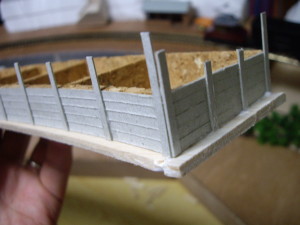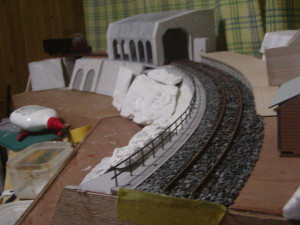保津峡
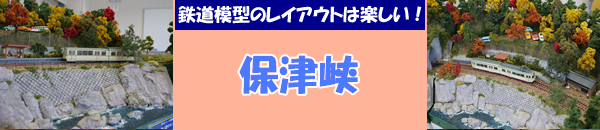
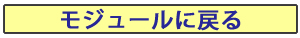
私は長年にわたってNゲージだけを楽しんで来たのですが、当時hataさんのHNモジュールに参加させて頂くにあたって初めてのHOサイズという事で、第1作はインパクトのある情景をと考えていました。
そして同時期に京都の嵯峨野にドライブに行き、嵯峨野のトロッコ列車の風景に感動し題材に決めました。
秋の風景でありながら紅葉が寂しかったので、3年後の2011年に背景モジュールを製作し紅葉のボリュームアップを図りました。
無人駅のモジュール
|
実在しない保津川という無人駅のモジュールです。季節は紅葉の秋。ホーム後方には落石止めの柵、
その上には展望台を兼ねた駐車場があり、ここも紅葉の名所になっています。
|
|
 隣の嵯峨野駅から駅員さん
が掃除や草花の世話をしに
来られます。 |
 この車両は、フランスのプロ
ヴンス鉄道の気動車です。
hatagさんのフルスクラッチ
ですが、全く違和感はあり
ません。 |
 駅の上方には、展望台を
兼ねた駐車場があり、紅葉
の季節には車から絶景が
楽しめます。 |
 水面まではもう少し高さが
ほしかったのですが、収納
の事を考えて、この高さに
おちつきました。水面に目を
合わせて見上げると、思っ
た以上に迫力のある絵にな
ります。 |
|
 高千穂鉄道の亀ケ崎駅をモ
デルに製作した待合室。無
人駅ですが、駅から下ると
しゅうらくがあるという設定
ですので通勤客もいます。 |
 最初は、小型機関車に数両
の小型客車という設定でスタ
ートしたクラブですが、今で
はこんなに長い連接車も普
通に入線してきます。 |
|
 保線小屋には作業員が
3人。車両の通過待ちです。 |
 一番広い所で600mmの幅
で、45度。カーブは730R。 |
|
 製作して8年もたって初めて気づいたのですが、
案内レールは普通、内側につけるらしいです。
前回の運転会で、inouさんとhatagさんに
ご指摘をうけました~。付け替えねば。 |
 駅の裏の駐車場に向かう、坂道の
途中の古~いセリカです。
新婚当時乗っていたので、夫婦で
乗ってると想像して楽しんでいます。 |
|
落石覆いのモジュール
|
無人駅のモジュールとはセットになっておりますが、左右どちらにも接続できますし、単体で他のモジュールと
繋ぐ事も出来ます。
落石覆いは、JR大和路線の大河原付近の物を以前画像を見て気に入っていて、これを参考に製作しました。
20m級の車両の通過と名鉄モ500がパンタを上げてぎりぎり通過できるように作っています。
|
|
 落石覆いは、曲線上という事もあり、
コンクリートの表現も必要でしたので、
製作は試行錯誤の繰り返しでした。 |
 トンネルと違って、車両が
ちらちら見えるのが、何とも
いい感じです。 |
|
 擁壁や岩盤の配置は、自然に
見えるように苦労しました。 |
 落石覆いの上は、草が覆い尽くす
感じにしたかったので、何回もやり
直しました。手前は、フォーリッジを
使用して、かつらのように少しめくれる
ようにしました。 |
|
 hatagさん製作の、DD13版の
嵯峨野トロッコ列車です。DE10
よりDD13の方が好きらしいです。
とてもいい感じですねぇ。 |
 小さな橋もアクセントとなっています。
上方から小さな渓流とともに流木も
流れついています。 |
|
 擁壁や落石覆いのコンクリート感や
それに続く岩場の表現等に苦労しま
した。 |
 保津川下りの船をいずれ作って
手を振るおばちゃんを表現したい。 |
|
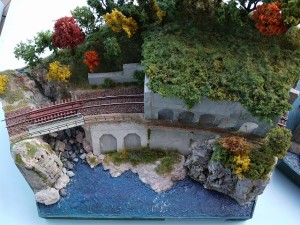 俯瞰からモジュールを見た所。
結構コンパクトです。 |
 メンテナンスの為に、落石覆いは
取り外しができるようにしました。 |
|
紅葉の背景モジュール
|
紅葉が寂しいので、紅葉のボリュームアップを図る為に背景モジュールを製作しました。
2台で約150本の樹木を製作しましたが、資金難の為に肝心の紅葉は少ないで
す。
|
|
 スタイロフォームを積み重ね、
形を整えていきます。 |
 2台を接続して確認。 |
|
 表面に、水に浸したプラスタークロスを
貼り、ボリューム不足の所は紙粘土を
盛り付けます。 |
 地表の塗装。10倍以上に薄めた
アクリル絵の具を、上から筆でた
たきつけるようにすると、何種類か
色が混ざって自然な色合いに。 |
|
 カラーパウダーやターフを散布 |
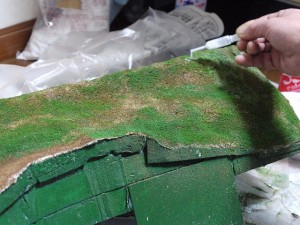 薄めた木工ボンド水溶液を使用して
固着していきます。 |
|
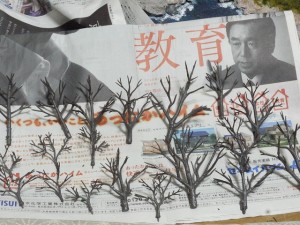 樹木の製作。枝ぶりを調整します。
カトーの樹木キットを何種類か使用。 |
 全部で150本ほど製作しました。結構
時間がかかりました。 |
|
 元の樹木を少し引き抜き、全体の
イメージを想像します。 |

|
|
 資金難の為、紅葉の数はすくないですが、
以前よりかなりボリュームアップとなりました。
緑が多いと紅葉がより映えていいですね。 |

継ぎ目は目立たないように処理しています。
|
|
 背景モジュールも専用の箱を
作りました。 |
|
|
| 製作過程 |
|
 2つのモジュールの土台を5mm合板
から切り出します。
2つで90度の角度、幅1200mmの
ラックに入れるとカーブは730Rに。 |
 脚の差し込み部分は5cmに決めて、
他の部材を切り出します。
線路のケガキを済ませておきます。 |
 組立ます。
コルク道床を敷いておく。 |
 脚は簡単な差し込み式にしたので、
先に差し込む側の部品を固定して
おきます。 |
 落石覆いはカーブにあるので、まずは
ボール紙で作ってみて、各部分の寸法
を細かくチェックしていきます。 |
 本体は、加工し易いバルサ材を
表面に使用、発泡ボードを補強
と内貼りに使用します。 |
 一応形にはなったものの、コンクリート
の質感をどう出すかが課題に。 |
 妻の部分は、特にコンクリートの
質感をだす必要があったので、
その部分だけをプラスターで製作。 |
 試行錯誤の上最終的に実施したのは、
バルサ材本体をストーン調スプレーで
塗装し、妻部分を接着。接合部を再度
ストーン調で筆塗りしました。 |
 ホーム後方の落石柵は、エバー
グリーンのT形材と細かい金網で
製作しました。 |
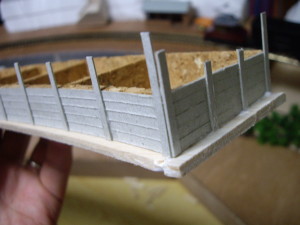 ホームはバルサ材を使用しました。
ボール紙の細い帯を貼っていきました。 |
 岩盤は、ロックモードにプラスターを
流し込んでいくつか製作。コンクリート
擁壁は、べニア合板のざらざらの方
で角棒を四角に組んで石膏を流し込み。 |
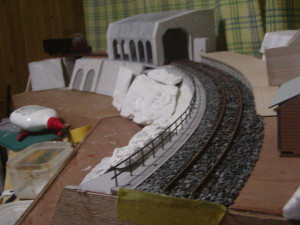 別に製作しておいた、岩盤や擁壁を
仮に配置していきます。線路はピィコ
の100番フレキシブルレール。バラスト
を撒いて柵を取り付けました。 |
 石積崖の所に目の細かい金網を
貼り、その上に紙粘土を厚めに盛
りつけしました。 |
 真鍮板で製作した四角いパイプを
押し付ける、紙粘土プレス製法で
作りました。溝に薄めた黒のアク
リル絵の具を流し、ハイライトを
付けます。 |
 渓流をまたぐ小橋は、HO用ガーター
橋をカットした両側を利用して、他は
プラバンを利用して製作。 |
 仮置きした擁壁や石崖を固着して
いきます。 |
 完成が見えてきました。この辺から
早く完成させたくてワクワクしてきます。
作業もはかどります。 |
 線路をマスキングして地面の塗装
を行います。 |
 樹木を製作。 |
 水面をアクリル絵の具で塗装。薄い色
から深い所は濃く塗装していきます。 |
 グラスポリマーメディウムを薄く
流し、24時間がまん。
|
誌面掲載

「にほんブログ村」に参加しています。
記事が気に入っていただけたら、クリックしていただけると幸いです